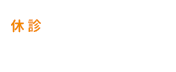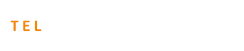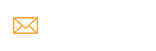本間真二郎 先生
2020年08月31日
コロナに関する発信もたくさんされていますので、ぜひ一度、チェックされて下さい。本間先生は医師でただ一人、我々の研究会(直立歯科医学研究会)に所属されています。
エリート医師が選んだ自給自足「マシーンから人になれたよう」

Copyright (C) 2020 Kobunsha Co., Ltd. All Rights Reserved.
医師で、栃木県那須烏山市にある「七合診療所」の所長・本間真二郎さん(51)は、寝る間を惜しんで西洋医学を究めるも、一転、栃木県での農業と自給自足を選んだ。里山に居を構え、家族と土を耕す。自家製野菜を育てながら、笑顔で暮らしている――。
「将来、医者をしている姿以外、イメージが湧かなくて。物心ついたころから、自分は医者になるって、直感的に思ってました」
札幌医大で勤務していた本間さん。優秀だった彼は32歳で、アメリカ国立衛生研究所(NIH)に招聘(しょうへい)される。ノーベル賞受賞者を100人以上出している、世界ナンバーワンの研究機関だ。
渡米を1週間後に控えた日の夜。同僚たちが、札幌医大初のNIH留学を勝ち取った本間さんの壮行会を開いてくれていた。
「あれは二次会の店に移動してすぐでしたね。誰かが『たいへんなことが起きてるぞ!』とテレビを点けたんです。そこに映し出されたのが、飛行機が高層ビルに突っ込む映像。アメリカ同時多発テロの瞬間でした」
画面を食い入るように見つめながら、本間さんはこんなことを考えていた。
「世界がひっくり返るようなことって本当に起きるんだな、と。いわゆる常識というものも、必ずしも正解ではないのかもしれんぞ、そんな思いがこみ上げてきました」
それでも、本間さんはアメリカで、充実した3年半を過ごす。その一方で、あの夜、芽生えた思いも、なかなか消えなかった。
「常識を疑って見るようになっていました。医療に関してもそう。西洋医学をガチガチに盲信していた自分自身の常識をまず、疑ってかかったんです。結果、西洋医学以外にも、人の健康に有意義な医療というのは無限にあるという確信に至りました。西洋医学にも素晴らしい面はいっぱいある。ただ、現代の医療は偏りすぎていると思えて仕方なかった」
帰国後。同医大初のNIH留学を経験した本間さんならば、あと数年、研究を重ねていけば、教授も遠くはないと思われたが。
「私は医療とは西洋医学だけじゃない、と気づいてしまった。そのうえで、西洋医学だけに偏りすぎ、それ以外を認めないような世界で上を、教授を目指すべきか……、本当にとても迷いました」
やがて、本間さんは決断する。医大を辞め、さらに生まれ故郷・北海道から去ることを。
「周りの人たちからは心配されましたよ。『頭がおかしくなったんですか?』って。あと、よく言われたのは『なにか宗教にハマったんですか?』とも(笑)」
そんな周囲の揶揄する声をよそに、本間さんは結婚したばかりの妻を連れ、しがらみのない栃木県に移住した。それは40歳のときだった。
同病院で助産師をしていた妻・リエさんはこう話す。
「すごく仕事のできる医師でしたね。でも、一方では人間離れした、精密マシーンのような人とも思われていました。いざ新婚生活を始めてみると……、会話が成り立たないんです。夫は自分が興味を持ったこと以外、話に乗ってこないというか。間違ったことは一切、言わないんですけど、それこそ、まるでAI、マシーンと暮らしてるみたいでした」
そんなとき、夫から切り出されたのが「大学を辞め栃木に移住したい」という話だった。リエさんは、これで何かが変わることに期待していた。
「だから、『本当はしたいことがある』と打ち明けられたとき、ホッとしたというか、そちらに進むほうがいいと思えたんです。驚くほど、夫は変わりました。いまは些細なことも笑いあえるし、彼との会話がとても楽しいんです。血の通った人間と暮らしているという実感がちゃんと持てるようになりましたね(笑)」
マシーンから人間へ、何が本間さんをそこまで変えたのか。すると当人、少し照れ臭そうな笑みを浮かべると、こう言葉を続けた。
「論文が評価されてアメリカに留学したり、大学内で出世して教授を目指そうとした私というのはきっと、他人に見せている自分だったんです。そこで考えたんです。本当の自分に嘘をつかない道はどっちだろうかって。そうやって選んできたから、人間らしくなれたのかもしれませんね」
「女性自身」2020年9月1日号 掲載